性的指向・性自認は「変わらない」という人の不都合な真実 福音派クリスチャンにとっての「変わる」とは?

目次
性的指向は 変わるのか 変わらないのか
1. 「憂慮する会」が呼びかけた署名は有効なのか?
NBUS(神のみことばに立ってセクシュアリティを考えるネットワーク)に対して立ち上げられたのが、「NBUSを憂慮するキリスト者連絡会」です。
「NBUSを憂慮するキリスト者連絡会」が最大の問題として訴えられているのは、「本人が願うなら…変化を助けるお手伝いをしていく」というこの文言です。(NBUS側からのキリスト新聞への意見書からの引用)
「憂慮する会」は、この文言一つをもって、客観的な証拠も挙げないままに、NBUSの目的は、転向療法を推し進めることであり、転向療法は非人道的行為だと批難されるのです。
文章構成の問題なのか、意図的なのか分かりませんが、「憂慮する会」の署名の呼びかけ文では、電気ショックを伴うような現在は禁止されている「嫌悪療法」と、セラピーとして実施される「転向療法」が混同して記されています。
NBUSは、「転向療法」にとどまらず、「嫌悪療法」まで行おうとしている、結果として、そのように誘導する文章になっています。
そのような呼びかけ文に基づく署名が、有効と言えるのでしょうか?
「憂慮する会」の主張が余りに飛躍しており、さまざまな論理的な矛盾を抱えていることは、すでに指摘させていただいた通りです。(「認知の歪みを指摘する」)
2. 思い込みが攻撃に変わるとき
なぜ、このような状況が生じているのか。
ずっと思い巡らしていますが、一冊の本を読んで、かなり整理ができました。
著者のダグラス・マレー氏自身、ゲイであることを公表しています。
彼が記したテーマが、『「差別主義者」というレッテル貼りにによって異論を封殺、行き過ぎた「多様性尊重」がもたらした社会分断と憎悪の実態。』と、カバーのそでにまとめられていました。
ダグラス氏は、1章を割いて、「ゲイ」をテーマに記しています。
一つ挙げられていた興味深いエピソードがありました。
デヴィッドソンという、以前はゲイだったという人物が、テレビ放送にゲスト出演して、証言した。
“35年にわたって妻と結婚生活を送っており、二人の子どももいる。他の人も自分と同じ人生を送れるのではないかと思い、団体を設立して、自由意志に基づいてカウンセリングを行っている”
これに対して、司会のピアーズ・モーガン(ゲイではない)が、“心の狭い最低の偏見持ち”と非難し、激高し、怒鳴り続け、一方的にトークを打ち切ってしまった。
半年後、デヴィッドソンが、自らの主張を肯定する映画の自主上映会を開催しようとしたところ、ゲイ向けのオンライン新聞の抗議を受け、直前になって、映画館での上演ができなくなってしまった。なんとか、別な会場を手配して、上映会が行われた。ダグラス氏もそこに出席していました。
ダグラス氏は、“私は、(転向療法を勧める)この人たちに怖れを抱いていない”と記しています。
“現段階においても近い将来においても、彼らは負け組”だからです。
この出来事に怖れを抱くには、様々な“憶測”が必要だとダグラス氏は言います。
“デヴィッドソンは、助けを求めてやってきた人にのみセラピーを行うと述べていたが、…あれは見せかけに過ぎず、やがては自発的な取り組みを強制的な取り組みに、そして一部分に対する強制を全体に対する強制に変えていく広大な計画の序章にすぎないのではないか” というように。
このような憶測が、思い込みに変わったのがこの一連の出来事でした。
“デヴィッドソンらが、参加者に異性愛への転向を強要するような行為があったとは証明できていない” し、“デヴィッドソンの「カウンセリング」がどのように行われているか、といったことさえ調査していない” にも関わらず、
“「自発的」は実際には「強制的」であり、「カウンセリング」は実際には迫害であり、デヴィッドソンの元にやってくる人はみな、異性愛者になることに否定的なゲイばかりであると思い込んだ”
ダグラス氏は、際限なく膨らむ疑念に警鐘を鳴らします。
“永遠の対立を回避したければ、他人の言葉に耳を傾け、それをある程度信頼する能力が欠かせない”と。
「憂慮する会」の言動が重なります。
NBUS側は、「本人が願うなら…変化を助けるお手伝いをしていく」と述べているに過ぎないわけですが、「憂慮する会」は、それは実際には強制であり、NBUSは、変化を望まないゲイに転向療法を施そうとしていると、思い込んだ。
そこには、怖れに増長された思い込みがあるだけで、何の証明も、調査もなされていません。
何の証明も調査もなく、相手の説明にも一切耳も傾けず、憶測と思い込みで相手を激しく非難する。
このようなことが、世界中で、そして日本でも繰り返されてきているのです。
言論の自由の危機であり、民主主義の基盤を揺るがすものです。
日本におけるLGBT運動が、左翼運動の変形として展開されていることへの憂慮を、自身ゲイである松浦大悟元参議院議員が著書で表明されていました。
「憂慮する会」の背景にも、極めて左翼的な、社会派とよばれるクリスチャンの存在があることを、私は認識しています。
3. 地雷にされた「変化」という言葉
余りにも感情的に激高していて、議論も成り立たない。それが、「憂慮する会」に対する私の印象です。
何が、「憂慮する会」の人々を、ここまで駆り立てたのか? なぜ、そこまで加熱してしまうのか?
きっかけは明らかに、NBUS側が発した、「変化」という言葉です。
ではなぜ、「変化」という言葉が、これほどの拒否反応を引き起こしてしまうのか。
そのことも、ダグラス・マレー氏の著書を読んで、得心しました。
ダグラス氏は、こう告げます。
“同性愛に対する姿勢を変えるのにもっとも貢献した道徳的要因は、同性愛は後天的な学習行動であるという考え方から、同性愛は生得的なものであるという考え方への変化にあった。”
“同性愛は生得的なものである” という考えが、社会の認識を変えるために、非常に重要だったと言うのです。
なぜなら、“自分の力ではどうしようもない特徴を持っている人をおとしめたり、見下したり、罰したりしてはいけない” という道徳規範が、強く現代社会にはあるからです。
同性愛者のある人々は、性的指向は「変わる」という言葉を、自分の個性に対する攻撃だとみなし、きわめて侮辱的なものとしてとらえる傾向があると、ダグラス氏は語ります。
「同性愛は一時的なものすぎない」という考えが、非人道的な嫌悪療法をもたらし、当事者を苦しめてきた過去があるからです。
だからと言って、「変わる」という考えを封じ込めてしまっていいのか。封じ込めるものなのか。
ダグラス氏が指摘するのは、“私たちはいまだ、一部の人間がゲイになる理由について、ほとんど何も知らない”という事実です。
アメリカ精神医学会は1973年に、WHOは1992年に、同性愛を疾患として扱う科学的根拠はないと判断しました。
“だが、ゲイが精神疾患でないことを受け入れたからといって、ゲイは生来のものであって変更はできない、ということにはならない” のです。
同性愛が社会に受け入れられた最大の要因は、「同性愛は生得的である」という主張にある。
しかし、実際のところ、「同性愛が生得的であるという科学的証拠は挙がっていない」
ここには、何より大きな、不都合な真実が横たわっています。
この不都合をねじ伏せようと、激しいバッシングを重ねて行った先に、何が待っているのでしょうか?
人権先進国であったはずの欧州のあちこちで、「極右政党」が台頭してきているとの報道を目にします。
揺り戻しは、すでに始まっているのかもしれません。
NBUSに対して、松谷編集長(キリスト新聞社)は、twitterで「極右」と言って切り捨てていました。
その実態は何なのか。どういう背景から生じているのか。
そこに切り込まないで、ジャーナリストを名乗れるのか。疑問です。
4. 生得的だと自明なゆえのジェノサイドがある
私にはダウン症の子がいます。ダウン症は明確に生得的な障害です。
なぜ、そう言えるのか。“医学的な検査で確認できるから”です。
出生後間もなく、ダウン症の疑いがあると言われ、筋肉の弛緩、小指が極端に短いなどの外見的な特徴が挙げられました。
しばらくして、染色体検査の結果が出ました。顕微鏡写真には、細胞の中に三つの赤い点がはっきり見えました。
21番目の染色体が三本。21トリソミー、すなわち、ダウン症だということです。
あんまりきれいだったので、「写真撮っていいですか?」と尋ねたら、医師が困惑されていたのをよく覚えています。
このように、染色体異常は、医学的な検査で確認できます。
では、性的指向、性自認を、出生間もない赤ん坊から検査できるのでしょうか。
そんな方法はありません。
医学的な検査方法もないのに、どうして性的指向、性自認は生得的だと断言できるのでしょう。
あまりに非科学的な主張です。
そもそも、性の自覚というのは成長と共になされていくものです。
LGBTQの人々が周囲との違和感を覚えるのも、この過程においてです。
当然のことながら、生まれた瞬間から性的指向、性自認に違和感を覚えている人などいません。
出生直後から、さらには胎児の時から、性的指向、性自認を検査する術がないことは、本当に幸いなことだと思います。
もし、そんな方法があったなら、過酷な同性愛者差別のある共産主義国やイスラム教国において、LGBTQの赤ん坊は、生存も出生も不可能になるかもしれません。
あまりに極端なことを言うと思われる方もいるでしょう。
しかし、現実に、ダウン症を含めて、あらゆる染色体異常の障害児は、出生すらできなくなってきています。
日本において、出生前診断が気軽にできるようになった結果、染色体異常と診断された胎児の98%は、堕胎されています。
数年前のデータなので、数値はさらに上がっているでしょう。
出生前診断が義務化されたアイスランドでは100%だと聞きました。
ダウン症をはじめとする染色体異常を抱えた子は、誕生すらできなくなりつつある。
これこそ、現代において、先進諸国から先行して、世界的に、静かに、急激に進行しているジェノサイドです。
性的指向、性自認は生得的だと主張し、異論をねじ伏せようとする人々は、この現実を見据えているのでしょうか。
そうでないなら、あまりに浅はかだと思います。
5. 絶対に変わらないとは、誰も言えない
かつて、LGBTQに対して電気ショックを与えるなどして治療しようとしたことがありました。
「嫌悪療法」と呼ばれ、現在は、アメリカでも日本でも、世界の多くの国で禁止されているものです。
その方法自体の残酷さから言っても、禁止されたのは当然のことだと思います。
性的指向や性自認を医学的な治療によって変えることはできない。
このことは、体験的に確認されてきたと言えます。
セラピーによって、性的指向、性自認の変化を促すのが「転向療法」です。
「憂慮する会」の推薦映画「Pray Away」では、ゲイ団体『エクソダス』が推進した「転向療法」によって、深い精神的ダメージを負った人々の告白が取り上げられていました。
転向療法で性的指向、性自認を変えることはできないと強く主張する人々がいます。変わったという人も、洗脳状態が解けると非常な苦痛を感じることになると。
一方で、変えられたと主張する人々がいます。今もなお転向療法を実施している人もいます。
では変わったのか、変わっていないのか、客観的に診断する方法はありません。
ここが難しいところだと思います。
変えられなかった、変わったと言ったけど嘘だった、それは、当人の言われる通りです。
だからと言って、変わったと言い続けている人もすべて嘘だ、と言い切ることもできません。
私自身は、「転向療法」は非常な危険性をはらんでおり、行うべきではないと考えます。
セラピーとは、あくまでも本人の意思で行われることですが、本人の意思で選んだと言っても、無意識に同調圧力がかかっていることがあります。
映画「Pray Away」でも、保守的な家庭で生まれ育ったレズビアンが、セラピストのところに連れていかれ、自分を変えなければと無理を重ね、変わったと主張する一方で、自傷行為を繰り返していたとありました。
この教会のセラピストが、聴衆受けを狙って、彼女に性的暴行を受けた経験を話すように迫ったという告白には、驚きました。
それが事実なら、二次被害、セカンドレイプです。
カルト化した教会と、転向療法が結びついたら、甚大な人権侵害が生じかねないと懸念を覚えました。
決して人権侵害になることのないように、抑圧的、支配的なありように対して敏感であるかどうか、問われることだと思います。
ここで、“福音派”と十把一絡げにしても害悪なだけです。
一口に福音派と言っても、日本だけでも何百もの教団、教派があります。単独で存立している教会も多く、小さな家の教会など含めれば、誰も把握できません。ありようも様々です。
個別の検証が求められると思います。
付記:転向療法について
「転向療法」には、個人的に反対だという私の意見に対して、そもそも「転向療法」の定義づけ自体が、あまりにも曖昧で、大きな問題をはらんでいるという指摘をいただきました。
現状では、カウンセリングやメンタリング、コーチング、個人的な相談にのったということすらも「転向療法」とされてしまう可能性がある。
確かにそうなったら、なにもできないことになります。
また、「転向療法」についての様々な調査結果をまとめた資料も、先日いただきました。
2000年代の最近の調査結果に基づく、様々な研究者の複数の調査結果をまとめたものです。
それが明らかにしているのは、転向療法を受けた過半数が何らかの変化を体験し、安心や幸福感を味わっており、悪くなったという報告は、数%にとどまっているということです。
「転向療法の害を記録する」という論文のタイトルが、「性的指向の変化」に変わった研究もありました。
調査を進める過程で、参加者の多くが、安心感、希望、自尊心の向上、人間関係の改善といった好ましい変化を覚えていることが明らかにされたからです。
転向療法についての害を語った参加者もいますが、複数の調査で、数%~10%前後にとどまっています。
心理療法は、様々な精神疾患に関しても行われている訳ですが、害を受けたという人の割合は、他の心理療法と比較しても大差ないということもあげられていました。
リンクはこちら➡ Dr. Ann E. Gillies,May 2020.
福音派のクリスチャンが「変わる」という、その意味
1. 変わっても、変わらなくても意味がある
「本人が願うなら…変化を助けるお手伝いをしていく」
NBUSが、「変化」という言葉を使われたことを、私はよく理解できます。
現実に、「私は変わった」と証言される元LGBTQの方は存在します。
映画「Pray Away」にも、変わったままと言う元ゲイ・トランスジェンダーも出演していました。
興味深いのは、彼は転向療法を受けていないということです。
彼自身は、転向療法が厳しい非難にさらされて大幅に縮小を余儀なくされた、その後の世代の人です。
「イエス・キリストが、自分の罪のために十字架で死んで、復活した」
これが、聖書の救いの教理の中心であり、「福音」と呼ばれるものです。
この「福音」を信じて、信仰によって自分は変えられた。それが、彼が語っていることです。
“どんな人でも変わることができる” というのは、福音派クリスチャンの信仰の大切な一部です。
罪人である人間は、自分も他人も変えることはできない。
しかし、神にはできないことはない。と信じるのです。
この点で、強制的に他者を変えようとすることは、本来の福音派の信仰からは外れます。
人が変わりうるとすれば、福音を信じたことによって、神が変えてくださるということです。
福音派クリスチャンが、人は変わるというときには、この信仰が大前提です。
福音を信じていない人には、関係のない話なのです。
人はただ、信仰によって変わることができる。
では、変わらなかったら、信仰が浅いということになるのか。そうではありません。
変わるとか変わらないとか、癒やされるとか癒やされないとかは、神が決められることです。
新約聖書の多くの書簡を書き記した使徒パウロは、自分には、癒やされないままの「とげ」があると告白しています。
取り去ってくださるよう何度も神に願ったが、かなわなかった。
間違いなく、最も信仰深い信者の一人である使徒パウロがそうだったのです。
変わるか変わらないかは、自己責任ではなく、神の責任なのです。
当人の信仰深さは関係ありません。
福音を信じたLGTBQのクリスチャンの中に、変わった、変えられた、と告白している人がいます。
劇的に変えられた、と言う人もいれば、行きつ戻りつ、今現在、変えられつつあると言う人もいます。
そしてやはり、変わらない、と言う人もいるわけですが、それは、信仰の深い、浅いの問題ではありません。
変えられたなら、神の一方的な恵みです。
変えられないままなら、そこにも何か、神の意図があるということです。
2. 大切なのは、ただ信じて救われた、この恵みを喜ぶこと
“ただ福音を信じて救われる” それが、救いの大原則です。
自分の罪を矯正したから救われるわけではありません。そんなことは誰にもできないのです。
頑張って自分を変えられるなら、信仰など不要です。
このことは、当然、LGBTQ当事者にもあてはまります。
性的指向、性自認を変えなければ救われないということではありません。
どんな人でも、ただ福音を信じた瞬間に、信じたというそのことのみによって、救われるのです。
この信仰の原則が徹底されていたなら、『エクソダス』の転向療法のような悲劇は起きなかったでしょう。
教会、クリスチャンが、道を外れてしまう時というのは、例外なく、自分たちでなんとかしようと自分の力に頼っている時です。
変わる、変わらない、癒やされる、癒やされない。というのは、一つの結果に過ぎません。
変わることもあれば、変わらないこともある。
どちらにしても、福音を信じたならば、その人は救われて、永遠に神の子どもとされています。
変われないのは、信仰が足りないからだ、と言う教会、クリスチャンはやはり、原則から外れているのです。
すべての人に差し出されている福音という神の恵み。
それは、「神であるイエス・キリストは、あなたの罪のために十字架にかけられ、葬られ、死を打ち破って復活された」ということです。
このことを自分自身のこととして受け入れる。イエスは、まさにこのような方だと信頼する。
それが信じるということです。
信じた瞬間に、その人は救われているのですから、そのことを喜んで歩んでいけばいいのです。
「Pray Away」の出演者の一人、ジェフェリー氏は、フリーダム・マーチ(自由の行進)という会を主催しています。
その会の目的は、「元LGBTQの多様なグループが、キリストのからだとされた証しを分かち合い、キリストにある自由を祝うこと」
「キリストのからだ」とされるというのは、福音を信じた人は皆、時代も国も超えて、キリストにつながれている。ということです。
教会というのは、究極的には、時代も国も教派教団も越えた、一つの共同体なのです。
過去・現在・未来において、普遍的に存在するたった一つの教会。これを普遍的教会とも呼びます。
フリーダム・マーチ(自由の行進)とは、福音を信じて救われた、その喜びを分かち合う、そのためだけの場所なのでしょう。
フリーダム・マーチのホームページやFacebookを見ました。いろんな人の証しが挙げられていました。
すっかり変わったよ。という人もいれば、変わりつつある途上だよ、と言う人もいました。
大切なのは、福音を信じて救われた、その喜びと自由を味わうこと。それだけです。
3. 救われた、という確信が与えてくれる日々の平安
福音を信じて罪赦された。一瞬の出来事である救いは、永遠の神の約束です。
しかし、私は救われた、と喜んで歩みだしてまもなく、誰もがつまずくことになります。
信じて救われたはずなのに、性懲りもなく罪を犯して愕然とさせられるのです。
この肉体や精神に、変わらずこびりついている罪があります。
信じたばかりのクリスチャンは、言って見れば、生まれたばかりの「みにくいアヒルの子」。
神の目には、美しい白鳥となった姿が見えていて、将来は約束されているわけですが、私たちの現実とは、あまりに大きな隔たりがあるのです。
救いは一瞬の出来事ですが、変わっていくには、時間が必要です。
多くの場合、その変化は目に見えて分かるようなものでもありません。
神は、私たちがまたしても罪を犯すことなどご存じで、その上に、解決策を示されています。
罪を犯してしまったなら、神に告白して、悔い改めて立ち返りなさい、と。
その罪もゆるされて、また、新たな一歩を踏み出していけるのです。
さいごに. 変わるとは、どこまでも信仰の問題
このように、福音派のクリスチャンが、変わる、変わらないというとき、それは、どこまでも信仰の問題です。
変わる、変わった、というのは、福音を信じた結果です。
変わるにせよ、変わらないにせよ、福音を信じないことには、どうにもなりません。
クリスチャンが、「変化を助けるお手伝い」ができるのは、福音を信じたクリスチャンに対してだけです。
そして、信じるというのは、自発的な神への応答です。形ばかり、信じますと言っても、まったく無意味です。
本人の意思に反して性的指向や性自認を変えることなど、誰にもできないように、誰に対しても、無理やり福音を信じさせることなどできないのです。
信じていない人に、クリスチャンができるのは、福音を伝えること、それだけです。
ただ福音を信じるなら、その人は、神との個人的な関係において、神によって救われます。
その信仰とは、福音を信じるということ。
福音、ギリシャ語では「エウアンゲリオン」、「よいしらせ」という意味です。
福音の内容は、“神の御子イエス・キリストは、私の罪のために、十字架にかけられ、死んで葬られ、死を打ち破って復活された”ということです。
福音を信じて、神の恵みによって救われる。ただ、それだけのことなのです。



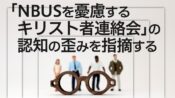


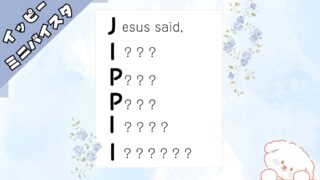

Comment
大変素晴らしい考察を感動を持って読ませて頂きました。ありがとうございました。欧州で台頭しているのが「極右」政党との表現だけが残念です。メインストリームメディアが意図を持って用いている用語は慎重に使用される事をお勧めします。
コメントありがとうございます。励まされます。
そうですね。「極右」という言葉は、「背景を考えるべきではないですか」、という投げかけの意味も込めて、そのまま使ったのですが、分かりづらかったかもしれません。
意図を強調する形で、若干、付け加えておきました。
ますます増してくる、闇の力をまじまじと感じさせられています。
私達がするべき事はなにか?
それは、主の福音を信じること、そして、その福音の上に聖化の段階を踏むこと、そしてなにより福音を伝えること。イスラエルに霊的な妬みを引き起こさせる事。
至って単純なんだと毎回思わされます。私達がどんなに努力しようが、神様の力にはなにも勝てないのですね。
最近、反出生主義という物をジェンダー関連の事を調べている時に知りました。ダウン症に関する事を究極にした考えだなと思わされています。
グノーシス主義からくる、神の想像に対する反抗の力はもっと強くなるという事を忘れずに主の福音に立っていきたいと思います。
ストレス、辛いこと、心の問題、これらの問題をすべての物や、人に一般化するような所に、結局は福音しかないんだという事を強く思わされます。
神の守りがありますように、祈ります。
コメント、ありがとうございます。
とても励まされます。
反出生主義、なるほど。
肉体を否定的に捕らえたグノーシスは、使徒の時代にすでにはびこっていた異端ですが、共通するものを感じました。
罪と死のただ中に陥っていった先に、命を根本から破壊する闇がありますね。
ただ福音を信じれば、神によしとされる道がある。
この道を歩み、伝えていきましょう!!